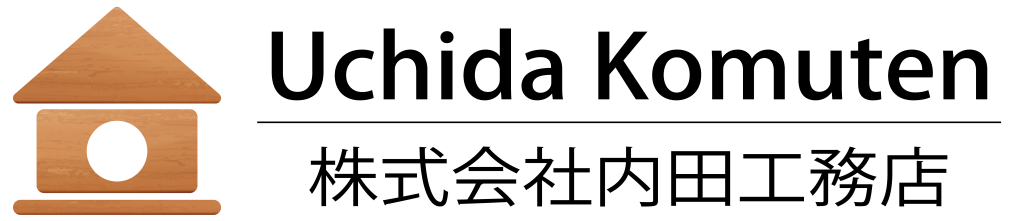前回に 引き続き 屋根の話
今回は③デザイン
現在の流行は「デザインハウス」「BOX型ハウス」と言われるもので
片流れで軒ゼロの家が 頻繁に見られる
わしが 若い頃(設計事務所時代)
有名建築家の設計した建物を 漁るように見て回り
「マス(BOX)」の組み合わせの家が かっこいいな と思った事もある
熊本のアートポリスは 5回以上 視察に行き
島根・鳥取・広島・山口の主要な 有名建築家の作品で
「新建築」「SD」に紹介された物は ほぼほぼ網羅して視察に行った
槇文彦さんの「ヒルサイドテラス」を わざわざ見に行った時も
「かっちょいいなあ~」感心した物である
「面で処理する」建築様式は
ちゃんとBOX組み合わせの美しい処理がしてあれば
それはそれで 美しいと思う
実際 設計事務所を退社し
地元のH工務店で設計課長になった5年間で 軒ゼロも数件設計した
H工務店を退社し 自分で内田工務店を始めた初期には
一件だけ 一部軒ゼロのBOX型の住宅を手掛けた
父親の代から 建築(主に住宅)を 見てきて 携わって来て
屋根について 思うのは
「軒があって 切妻の形状が 住宅には一番ふさわしい」という事
「軒がある事」で 雨漏りリスクの多くは軽減されるし
「軒がある事」で 外壁の傷み具合も外壁からの雨漏りも軽減される
寄棟は 棟廻りでの換気方法が「棟換気」「塔屋の設置」しかなく
軒先換気をしていても その軒先で 本当に換気が出来ているのか
と言うと かなり「怪しい」話になってくる
熱は「棟の頂部」に集まるのに
「屋根下端の軒先(軒天井)で換気する」という方式は
心情的にも現場経験からも 違うんじゃないかと思う
棟頂部で 換気した場合
当然下地のルーフィングを切断することになり
棟換気金物の台風強度は40mなので 台風には対抗できず
棟換気による台風被害を100件以上見てきた経験から
棟換気・塔屋換気は NGだと思う
片流れであっても 流れ頂部の軒裏の換気に対して
十分な雨漏り防止対策をすれば これはこれで良いと思う
JIOが集計した 雨漏り事故ランキングで
片流れ75% 切妻15% 寄棟6% という数字があるが
片流れの多くが 「軒ゼロ」納まりにしているケースが多いため
極端に割合が大きくなっているだけで 軒をちゃんと出して
軒裏での換気を 雨漏り対策すれば それほど恐れる物でもないと思う
南面の頂部で片流れで処理した「巣籠りの家(=内田工務店の作品)」では
建築後10年以上は経過したが 雨漏りは起きていない
台風・風当りの強い「南面」へと 勾配を付けざるを得ないケースだったので
「軒裏の防水処理」「軒裏換気の防水対策」は かなり趣向を凝らした納まりとした
「ちゃんとやったら ちゃんと漏らない」そう思う
内田工務店で 20年前に建てた「天文台の或る家」では
ファサードは 土地柄を考慮して「蔵」のデザインで 瓦+しっかりとした軒の形だが
裏手の 道からあまり見えない所では 天文台を載せるために
フラット屋根(FRP防水)として 笠木の小さいパラペット納まりとした
設計事務所時代のデザインの憧れを そのまま具現化した
のだが
20年たって 悲しいかな 軒がゼロ(パラペット納まり)の部分は
サイディングからの漏水が 所々起きて 全面張替えをした
20年間 コーキングの打ち直しも再塗装もしなかったせいも
少しはあるかも知れないが
正面の軒のある部分の被害は ほぼゼロなのに
軒の無い部分は被害あり である現実に
「やっぱり軒は 作るべきだ」自分の失敗に 意識再確認した
リフォームしながら 自分の子供の様な作品(=天文台の或る家)が
傷ついているのを見るにつけ 悲しい思いになってしまった
今回の改修では パラペットに 大きめの笠木をつけて
大きめの笠木の下から 壁通気の逃げ道を作ったので
今回の様な短命には終わらない確信がある
が にしても ちゃんとした軒ではなく せいぜいが20cm位なので
内田工務店の全ての作品に共通している「樋を含めて90cmの出」に比べると
まだまだなので
当初計画の甘さを 自分自身 反省している
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
「デザインハウス」「軒ゼロ」が かっこいい
と言う 風潮が あるように思うが
それって 本当に建て主が望んでいる事なのか?
緩勾配の板金屋根にして 屋根コストを抑え
軒裏をゼロにして 軒裏工事費と屋根面積を抑えて
結局コストダウンの為にやっているだけではないか?
何度も言うが 軒ゼロは 外壁への雨の負担を増やし
軒ゼロ故に 軒先の防水処理が 困難になり
ちゃんと 幕板(破風)を大きくとって雨をかかりにくくした上で
軒先換気をとるとか
ちゃんと 頂部のパラペット笠木の懐を大きくして
暴風時の影響を 少なくしたうえで パラペット換気をする
とか 処理した上での 「軒ゼロデザイン」なら まだ 納得出来るのだが
屋根の軒裏からの漏水は それで逃れられたとして
外壁への雨の負担には 全く考慮しない「軒ゼロ」の家を
そうまでして 建てていく必要は 本当にあるのか?
もちろん土地柄はあって
京都に視察に行った時 その現場もやはり「軒ゼロ」なのだけど
隣地とのスキマが30cm程度で 建てていて
「京都で30坪40坪の土地って贅沢なんですよ」という工務店の話を聞き
そりゃあ そんなに土地が高かったら 敷地いっぱいに建てるし
軒もゼロになる
ただ 建物同士が近接しているので その間の壁は
少々では雨漏りしない感じがする
わしが 生活しているのは山口県で
土地も60坪 100坪は 当たり前の状況で
わざわざ 軒ゼロの家を 提案する気は
わしには 無いのですよ
「かっこいい」って それって 本当に建て主が思っているのか?
ローコストにして売らんがためのキャッチコピーに なっていないか?
それだけのリスクを冒して 軒ゼロにする必要があるのか?
何件か 自分でやっておいて 言うのも難だが
数件 やってしまった 反省は 自分自身 深いのですよ
「建て主」が望んだのでは無くて
「自分の好みで提案した」と 思い返せば 思い上がりだったと感じる
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
軒ゼロを 味噌くそに書いたが
外壁が タイルや塗り壁なら 雨漏りリスクは 軽減される
これは 「壁編」で カキカキするので ここでは割愛
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
屋根が 瓦だと 「屋根の主張(存在)」が 大きくなるので
屋根の向き・軒の出・形状を 建物のマス(ボーリューム)と見比べながらの
デザイン手法になる
奇抜なデザインには ならないが
「すっきりと見せる」そんな瓦屋根・切妻の家が
わしの方針です
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
他にも 滅茶苦茶 色々あるが
「屋根」の概要は これ位で終了
次回のテーマは 決めていませぬが
週一ペースは 頑張ります